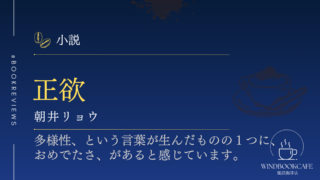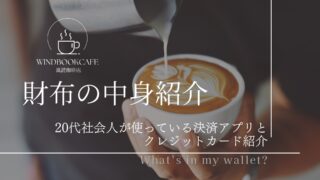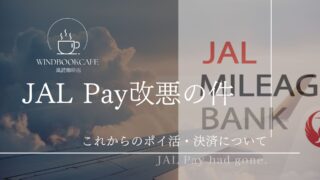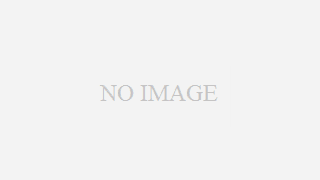こんにちは。風読珈琲店のカエデです。
金融庁が2026年度の税制改正に向けて提出した要望の中で、特に注目されているのが NISAの拡充 です。この改正が実現すれば、未成年から高齢者まで、より幅広い世代がNISAを活用できるようになり、日本の資産形成環境が大きく前進する可能性があります。
今回は、2026年度以降に求められているNISA拡充案についてまとめます。
なぜ今、NISAの拡充が求められているのか?

金融庁は「資産運用立国」の実現を掲げ、国民の資産形成を支援するために、以下の目的・課題間をもとにNISA制度のさらなる充実を目指しています。
- 若年層や高齢層を含めた 全世代の資産形成支援
- 「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、家計の資産形成を促進
- 投資初心者でも安心して利用できる制度設計の必要性
改正要望の主なポイント

改正要望のポイントは以下の3点です。
未成年へのNISA解禁
現在の新NISAは18歳以上が対象ですが、金融庁は「つみたて投資枠」に限って 0歳からの利用 を可能にするよう求めています。
これは、子育て支援の一環として、こども家庭庁と共同で要望されたものです。
メリット
- 教育資金や老後資金の早期準備が可能
- 長期・非課税・複利の効果を最大限に活用できる
- 子どもが自然に投資教育を受ける機会になる
高齢者向け商品の追加
高齢者のニーズに応えるため、 毎月分配型の投資信託など、定期的に収入が得られる商品をNISAの対象に含めることが検討されています。
毎月分配型の投資信託は、手数料が高い商品も多く、元本を取り崩す「タコ足配当」のリスクもあるため、慎重な商品選びが必要です。
スイッチング(商品の入れ替え)制度の導入
現行制度では、NISAで購入した商品を売却すると、その年の非課税枠は復活しません。
改正後は、 同じ年のうちに別の商品へ乗り換える「スイッチング」 が可能になるよう要望されています。
検討中の論点
- 利益を含めた全額で乗り換え可能か?
- 元本のみのスイッチングになるのか?
子供NISA誕生の可能性

「子供NISA」の誕生に向けた動きは、金融庁が2026年度の税制改正要望として提出した内容の中でも、特に注目されています。これは、かつて存在した「ジュニアNISA」の反省を踏まえ、より柔軟で実用的な制度として再設計される可能性があります。
ジュニアNISAとの違い
「ジュニアNISA」は2016年に導入されましたが、以下のような制約があり、利用が伸び悩みました。
- 18歳までの払い出し制限
- 制度の終了が決定(2023年末で廃止)
- 投資教育や資産形成の観点からは魅力が薄かった
子供NISAの特徴(想定)
金融庁がこども家庭庁と共同で要望している「子供NISA」は、以下のような特徴を持つとされています。
- 対象年齢の引き下げ:0歳から利用可能(つみたて投資枠に限る)
- 年間投資枠:120万円まで
- 非課税期間:無期限
- 払い出し制限:なし(ジュニアNISAとの最大の違い)
この制度が実現すれば、親が子どもの将来資金(教育費・老後資金など)を早期から準備できるだけでなく、子ども自身が自然と投資教育を受ける機会にもなります。
投資教育の効果
子供NISAの導入により、以下のような教育的・経済的効果が期待されています。
- 長期投資の習慣化:複利の力を実感しながら資産形成を学べる
- 金融リテラシーの向上:家庭内での資産運用の会話が増える
- 自立支援:大学資金や独立資金の準備がしやすくなる 1
贈与税がかかるケースとは?
日本の贈与税制度では、年間110万円を超える贈与を受けた場合、その超過分に対して贈与税が課税されます。
たとえば、親が子どものNISA口座に毎年120万円を入金した場合、110万円を超える10万円分に対して贈与税が発生する可能性があります。
また、以下のようなケースも注意が必要です
- 毎年同じ金額・同じ時期に贈与していると、「定期贈与」とみなされる可能性がある
- 名義は子どもでも、実質的に親が管理していると「名義預金」と判断されることがある
贈与税対策の具体例
年間110万円以内に抑える
贈与税の基礎控除額(年間110万円)以内であれば、贈与税はかかりません。
たとえば、子供NISAの年間投資枠が120万円でも、110万円までの入金にとどめることで非課税にできます。
入金額やタイミングを毎年変える
毎年同じ金額・同じ時期に贈与すると「定期贈与」とみなされるリスクがあります。
そのため、金額や入金日を変えることで、都度の贈与であることを示すことができます。
贈与契約書を作成する
贈与の事実を明確にするために、贈与契約書を毎年作成するのが有効です。
契約書には以下の内容を記載します。
- 贈与者(親)と受贈者(子)の氏名・住所
- 贈与金額
- 贈与日
- 子どもの署名(可能であれば)と押印
これにより、税務署からの指摘に対して「一括贈与ではなく、都度の贈与である」と説明できます。
教育資金として直接支払う
学費や入学金などを親が直接学校に支払う場合、それは贈与とはみなされません。
この方法を使えば、贈与税の対象外で子どもの教育費を支援できます。
注意点:名義預金とみなされないために
- 子ども名義の口座に入金した後は、親が勝手に引き出さない
- 子どもがある程度の年齢になったら、本人の意思で運用や引き出しを行えるようにする
これらを守らないと、「実質的には親の資産」と判断され、相続税の対象になることもあります。
まとめ

今後のスケジュールについては以下が想定されます。
| 時期 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 2025年8月末 | 要望提出 | 金融庁が自民党財務金融部会などに要望書を提出 |
| 2025年末 | 税制改正大綱策定 | 与党が税制改正の方針をまとめる。ここで制度改正の方向性が決まる |
| 2026年初頭(通常国会) | 法案提出・審議 | 政府が税制改正法案を国会に提出し、審議・可決される |
| 2027年以降 | 制度開始(最速) | 実際の制度改正が施行されるのは、早くても2027年からと見込まれる |
今回の要望提出は、NISA制度の大幅な見直しに向けた 第一歩です。
この後、与党との協議を経て、年末の税制改正大綱に盛り込まれるかどうかが決まり、最速で2027年から新制度がスタートする可能性があります。
この改正が実現すれば、NISAは「若者の資産形成」だけでなく、「子育て支援」や「高齢者の生活支援」にもつながる、より包括的な制度へと進化します。
今後の動向にも注目してきましょう。